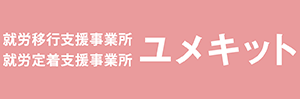こんにちは☆
本日は七夕ですね!
七夕と言えば個人的に短冊に願い事を書くイメージが強いですね。
学生時代の給食に七夕をイメージしたゼリーが出た思い出もあります。
では、七夕の発祥はいつからなのでしょうか?
なんとなく、日本発祥かな?と思いがちですが
(なんなら、筆者もそう思ってました。笑)
実は中国の発祥。
中国の乞巧奠(きっこうでん)という行事に、
日本古来より伝わる棚機津女(たなばたつめ)の風習が
結び付いたものと言われています。
中国では彦星は農業の星、織姫は養蚕や針仕事の星とされており、
織姫に倣って裁縫や手芸が上達するように願う行事である
乞巧奠が行われていました。
これが日本にも伝わり、奈良時代には宮中行事として行われるようになります。
一方で、日本には7月7日に神様の着物を乙女が小屋にこもって織る
「棚機(たなばた)」という行事がありました。
この棚機と乞巧奠が結び付いたものが、七夕の節句となったのだそうです。
——————
ちなみになぜ七夕では
短冊に願い事を書くのか?
それは、織物の上手な織姫にあやかって
「物事が上達しますように」と、お願い事をしたのが始まりだと言われています。
笹の葉に飾ると、織姫と彦星の力で願いが叶えられたり
悪いものから守ってくれるという言い伝えがあるのだそうです。
短冊と一緒に飾る、七夕飾り。
鶴は「長寿」
巾着は「金運上昇」
網は「大漁・幸せをすくい寄せる」
吹き流しは「魔よけ」
提灯は「正しく導く」
と、飾りにもそれぞれ意味が込められています。
—————–
近年では片づけが手間で
めっきり飾る機会が減ってしまった笹。
その代わり、ショッピングモールなどで
笹を飾るところが増えてきた印象もありますね。
短冊に願いを書くだけでなく、
星を見る、七夕ゼリーを食べる等、
今夜は自分なりの七夕を楽しんでみてはいかがでしょうか。